なぜ高気密住宅でカビが?プロが明かす根本原因と「本当の」対策
2025.11.14 BtoC カビ・結露対策 住まいの悩み 管理人
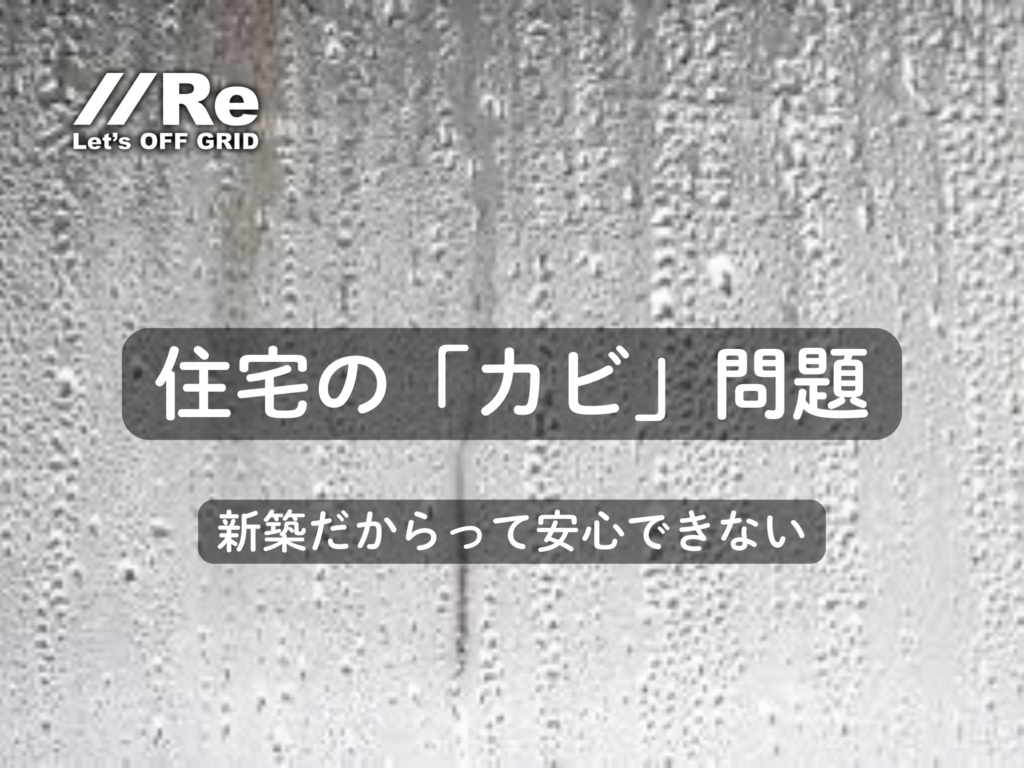
© Re 2025 執筆:株式会社 Re 髙橋 | 読了目安:約9分
なぜ高気密住宅でカビが?プロが明かす根本原因と「本当の」対策
目次
導入:そのカビ対策、根本的に間違っていませんか?
「最新の家に引っ越したはずなのに、クローゼットの奥がカビ臭い…」
「冬場、窓の結露がひどく、カーテンに黒い点々が…」
「いくらカビ取り剤で掃除しても、すぐに同じ場所に再発する…」
このようなお悩みはありませんか?特に最近の住宅は「高気密・高断熱」が主流となり、快適性が増した一方で、一昔前の「すきま風だらけの家」とは異なる、現代特有のカビ問題に直面するご家庭が増えています。
私(高橋)は、元・積水ハウスの営業マンとして、数多くの住宅とそこに住まうご家族の悩みを見てきました。その経験から断言できることがあります。
それは、表面的なカビ取り剤や、置き型の除湿剤だけでは、カビの根本解決にはならないということです。なぜなら、カビの発生原因は、皆さんが思っている「汚れ」や「湿気」といった単純なものではなく、住宅の「構造」と「暮らし方」のミスマッチにある場合がほとんどだからです。
この記事では、「住宅のプロ」の視点から、なぜ高気密住宅でカビが発生してしまうのか、その本質的な原因と、「本当の」対策について徹底的に解説します。
カビ対策で陥りがちな「3つの誤解」
本格的な対策に入る前に、多くの方が勘違いされているカビ対策の「誤解」を解いておきましょう。これを知るだけで、無駄な努力を減らすことができます。
誤解1:「カビ=不潔だから」という思い込み
もちろん、カビはホコリや汚れを「栄養」にします。しかし、それ以上にカビの発生に不可欠な条件があります。それは「温度」と「湿度」です。
- 温度: 一般的に20~30℃が最も活発。
- 湿度: 70%を超えると活発になり、80%以上で一気に増殖。
- 栄養: ホコリ、皮脂、石鹸カス、そして建材(木材、壁紙の糊など)
現代の住宅は、冬でも暖かく、カビにとって非常に快適な「温度」が一年中保たれています。あとは「湿度」という条件さえ揃えば、掃除が行き届いているように見える場所でも、カビは簡単に発生してしまうのです。カビ対策は「掃除」ではなく、まず「湿度管理」と考えるべきです。
誤解2:「換気扇を回していれば大丈夫」という油断
2003年以降に建てられた住宅には、シックハウス症候群対策として「24時間換気システム」の設置が義務付けられています。これは「1時間に家中の空気の半分が入れ替わる」ことを想定したシステムです。
しかし、このシステムが正しく機能していないご家庭が非常に多いのです。
- 「音がうるさい」「冬は寒い」という理由で、換気扇のスイッチを切っている。
- 壁にある「給気口」を閉じている。(これでは空気の入口がなくなり、換気扇は空回りします)
- 給気口や換気扇のフィルターがホコリで目詰まりし、十分な給排気ができていない。
24時間換気は、高気密住宅の「呼吸」を司る重要なシステムです。これを止めることは、家の呼吸を止め、湿気や汚染物質を室内に閉じ込めることに他なりません。
換気口のフィルターがホコリや汚れでひどく目詰まりしている状態。外側から見て、明らかに空気が通らなさそうな厚いホコリの層が見える。少し汚れた白い壁に設置されている。背景はシンプルで、換気口が主役。

誤解3:「カビは冬だけの問題」という先入観
「カビ=冬の結露」というイメージが強いかもしれません。確かに、外気で冷やされた窓や壁に、室内の暖かく湿った空気が触れて発生する「表面結露」は、冬場にカビの大きな原因となります。
しかし、実は夏場にも注意が必要です。エアコンで室内をキンキンに冷やした場合、壁の中や床下など、普段見えない部分で「逆転結露(夏型結露)」が発生することがあります。これは、外の高温多ifsな空気が、エアコンで冷やされた壁の内部に侵入して結露する現象です。
さらに、梅雨時の長雨や、近年のゲリラ豪雨による湿度の急上昇も、カビのリスクを高めます。つまり、**現代の住宅において、カビ対策に「オフシーズン」は無い**のです。
プロが明かす「高気密住宅」カビ発生のメカニズム
では、なぜ「高気密」であることが、カビの発生に繋がってしまうのでしょうか。それは、昔の「すきま風だらけの家」とは決定的に違う、高気密住宅特有の性質があるからです。
原因1:高気密化が招いた「空気のよどみ」
昔の家は、壁や窓に隙間が多く、何もしなくても自然に空気が入れ替わっていました。その代わり、冬は寒く、エネルギー効率は最悪でした。
一方、高気密住宅は「魔法瓶」のように家全体を密閉し、熱を逃がさない構造になっています。このお陰で、少ないエネルギーで快適な室温を保つことができます。しかし、その代償として、**意識的に空気を動かさないと、空気は全く動かなくなります。**
例えば、家具の裏側、クローゼットや押入れの奥、部屋の隅などは、空気が循環しにくく、湿気が集中します。この「空気のよどみ」こそが、高気密住宅におけるカビの最大の温床となるのです。
原因2:ライフスタイルの変化と「不十分な換気量」
24時間換気システムは万能ではありません。法律で定められた換気量は、あくまで「最低限」の基準です。現代の私たちの暮らしは、想定以上に多くの水蒸気を室内に発生させています。
- 在宅ワークや巣ごもりによる、在宅時間の増加(人の呼気や汗からも水蒸気が出ます)
- 共働きによる、洗濯物の室内干しの増加
- 加湿器の過度な使用
- 観葉植物、水槽(アクアリウム)などの趣味
- ガスファンヒーターや石油ストーブの使用(燃焼時に大量の水蒸気を発生させます)
これらによって発生する水蒸気の量が、24時間換気の排気量を上回ってしまえば、室内の湿度は上がり続け、カビのリスクは一気に高まります。特に、高気密住宅での「室内干し」と「加湿器のつけっぱなし」は、カビに餌をやっているようなものです。
複数の要素が複合的に写っている。部屋の一角で、洗濯物が室内干しされている(ピンチハンガーにかかった衣類など)。その近くで加湿器から水蒸気が出ている。背景に、リモートワークをしている人の後ろ姿が少しだけ見える(部屋の生活感を示す程度で、プライバシーに配慮)。全体的に少し湿気がこもっているような空気感(視覚的に表現は難しいが、間接照明などで工夫)。

最も怖い「壁内結露」のリスク
ここまでは「目に見えるカビ」の話でしたが、住宅のプロとして最も警鐘を鳴らしたいのが、「壁内結露(内部結露)」です。
これは文字通り、壁紙の内側や、床下、天井裏など、目に見えない部分で結露が発生する現象です。断熱材の施工不良や、防湿シートの隙間などから室内の湿気が壁内に侵入し、冷たい外壁(またはその逆)に触れて水滴となります。
壁内結露は、以下の点で非常に深刻です。
- 発見が遅れる: 気づいた時には、壁紙の内側がカビだらけ、床下の木材が腐っていた、というケースも少なくありません。
- 断熱性能の低下: 湿気を含んだ断熱材は、断熱性能が著しく低下します。
- 構造体の腐朽: 住宅の柱や土台といった重要な構造体を腐らせ、家の耐震性や寿命を縮める原因になります。
「最近、壁紙がフワフワと浮いてきた」「特定の部屋だけがカビ臭い」といった症状は、壁内結露のサインかもしれません。これは、表面的なカビ取りでは絶対に解決せず、専門家による診断と大掛かりなリフォームが必要になる場合もあります。
今すぐできる対策と「根本対策」の違い
カビのメカニズムがわかったところで、具体的な対策を見ていきましょう。自分でできる「応急処置」と、プロに任せるべき「根本対策」に分けて考えることが重要です。
まずは応急処置:湿度管理と空気の循環
これ以上カビを増やさないために、今日からできる対策です。
- 湿度計の設置: まずは敵を知ること。リビング、寝室、クローゼットなど、複数の場所に湿度計を置き、現状を把握しましょう。目指すは常時60%以下です。
- 24時間換気の再点検: スイッチは入っていますか?給気口は開いていますか?フィルターは掃除されていますか?今すぐ確認してください。
- 空気の循環: サーキュレーターや扇風機を使い、家具の裏やクローゼットに向けて風を送り、「空気のよどみ」を解消しましょう。
- 家具の配置見直し: 壁から5cm~10cmほど離して家具を配置し、空気の通り道を作ります。
- 除湿機・エアコンの活用: 湿度が60%を超える日が続くなら、我慢せずに除湿機やエアコンの除湿(ドライ)機能を活用してください。その際、部屋を密閉し、サーキュレーターを併用すると効率が上がります。
なぜ「プロの診断」が必要なのか?
上記の応急処置を徹底してもカビが再発する場合、あるいは「壁内結露」が疑われる場合は、残念ながらご家庭での対策には限界があります。
その原因は、以下のように住宅の専門知識がなければ特定できない領域にある可能性が高いからです。
- 換気システムの設計ミス(家の広さや間取りに対して換気量が足りていない)
- 断熱材の施工不良(熱の逃げ道=結露の発生ポイントになっている)
- 防湿層の不備(壁内への湿気の侵入を止められていない)
- 雨漏りや配管からの水漏れ
私たち「住宅のプロ」は、専用の機材(サーモグラフィーカメラ、壁内水分計など)を使い、目に見えない問題箇所を特定します。その上で、防カビ・防湿効果の高い塗料の施工、換気システムの増強、部分的な断熱改修など、その家に最適な「根本対策」をご提案します。
家の健康診断と同じです。自己判断で薬(カビ取り剤)を使い続けるのではなく、一度、専門医(プロ)の診断を受けることが、カビとの戦いに終止符を打つ一番の近道です。
エネルギーのプロが「カビ対策」を語る理由
「なぜエネルギー相談の会社がカビ対策まで?」と不思議に思われるかもしれません。 実は、カビ・結露に悩む家は、多くの場合「エネルギー効率」にも深刻な問題を抱えているのです。
例えば、断熱不良の箇所(熱の逃げ道)は、そのまま「結露の発生箇所」になります。 非効率な換気システムは、湿気を排出できないだけでなく、冬は冷たい外気を、夏は暑い外気をそのまま取り込み、冷暖房費を無駄に垂れ流していることになります。
私たちが目指すのは、単なるカビ退治ではありません。
「快適な住環境(カビのない健康な暮らし)」と「光熱費削減(エネルギー効率の最適化)」は、住宅性能を高めるという点で表裏一体です。
私たちは「住宅のトラブル/エネルギー総合相談窓口」として、カビや結露の問題から、光熱費の見直し、さらには太陽光発電や蓄電池の導入まで、住まいに関するあらゆるお悩みをワンストップで解決します。特定のメーカーに偏らない中立的な視点で、お客様のご家庭にとって「本当に」最適なプランをご提案できるのが、私たちの最大の強みです。
Q&A
Q. 除湿機を一日中つけていますが、それでもカビますか?
A. 除湿機は室内の湿度を下げるのに非常に有効ですが、万能ではありません。除湿機が効いているのはその部屋だけで、クローゼットの中や家具の裏側など「空気のよどみ」がある場所には湿気が溜まったままになっている可能性があります。サーキュレーターを併用して空気を循環させること、そして除湿機のフィルター掃除をこまめに行うことが重要です。
Q. リフォームや防カビ施工はどのくらい費用がかかりますか?
A. 原因や範囲によって費用は大きく異なります。壁紙の張り替えと防カビ処理程度で済む場合もあれば、壁を剥がして断熱材からやり直す大規模な工事が必要な場合もあります。まずはプロによる現状診断(無料)を受けていただき、原因を特定した上で、必要な対策のお見積もりをさせていただく流れになります。
Q. 相談したら、具体的に何をしてもらえるのですか?
A. まずは「元・積水ハウスOB」の知見を持つ専門家がご自宅にお伺いし、カビの発生状況、間取り、換気システムの状態、お困りごとなどを詳しくヒアリングします。必要に応じてサーモグラフィーなどで結露箇所を調査し、原因を特定します。その上で、対策(防カビ施工、換気見直し、断熱改修など)のご提案と、光熱費のシミュレーションなどを合わせて行います。もちろん、ご相談や診断、お見積もりは無料ですのでご安心ください。
想い:カビの悩みから解放された「本当に豊かな生活」を
カビは、見た目の不快さだけでなく、アレルギーや喘息の原因となるなど、ご家族の健康に直結する深刻な問題です。
毎日カビに怯え、掃除に追われる生活は、決して「豊か」とは言えません。
私たちは、エネルギーの専門家として、そして「住宅のプロ」として、皆様がカビの悩みから解放され、一年中クリーンな空気の中で、健康で安心して暮らせる「本当に豊かな生活」を手に入れていただくためのお手伝いをしたいと心から願っています。目指すのは、電力網や住環境のトラブルに依存しない、自律した快適な暮らしです。その第一歩として、まずは皆様の「住まいの困り事」に、全力で向き合います。
住まいの悩み、ワンストップで解決しませんか?
住宅のトラブル・エネルギー総合相談窓口
「カビが再発する」「光熱費が高い」「太陽光に興味がある」
その悩み、すべてまとめてご相談ください。
プロが中立的な視点で診断し、最適な解決策をご提案します。
