【緊急提言】能登半島地震で露呈した「福祉避難所が機能しなかった理由」と、今日から始める通信・電源対策
2025.09.11 医療・福祉・公共 管理人
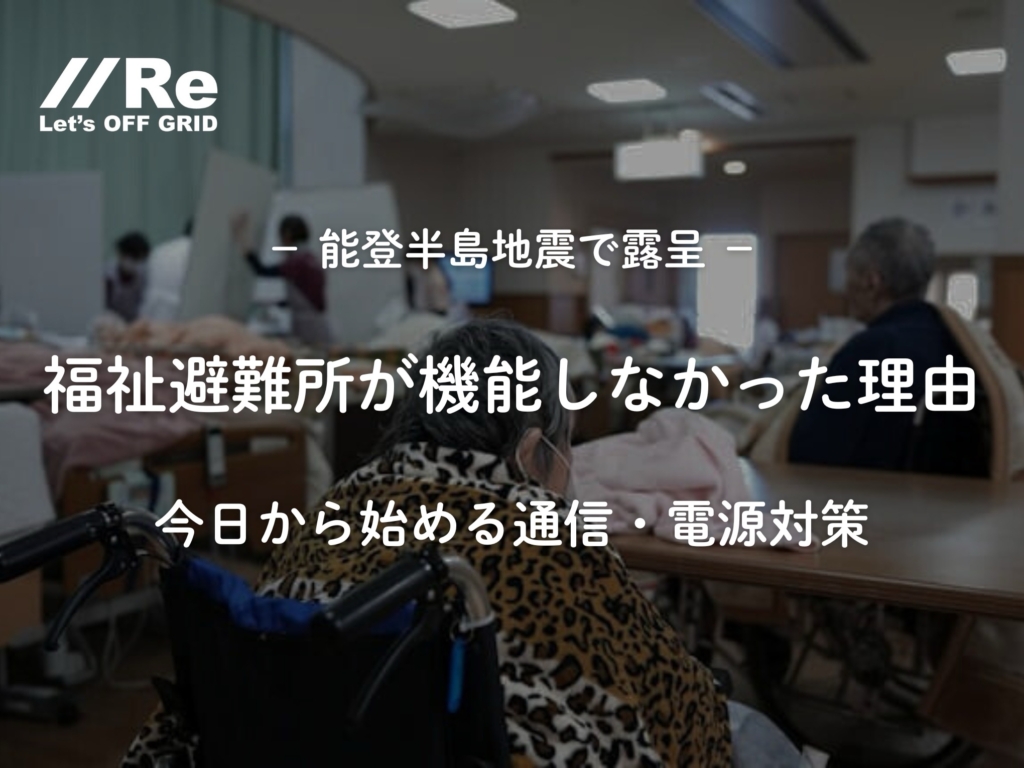
【緊急提言】能登半島地震で露呈した「福祉避難所が機能しなかった理由」と、今日から始める通信・電源対策
- 2024年1月1日の能登半島地震では、要配慮者を受け入れるはずの福祉避難所の多くが計画どおり開設・運営できなかった。
- 背景には通信と電源の同時停止、職員の被災、断水・衛生課題、施設被害など複合的要因がある。
- 行政側も「どこで何が起こっているか」を把握しづらい情報空白に陥り、初動調整が難航した。
この記事は、能登半島地震の教訓を出発点に、福祉避難所の通信・電源対策を中核とする現実的な備えを、愛知県(とくに蒲郡市周辺)の社会福祉施設・医療機関および東京都内の社会福祉施設に向けて、経営視点で整理したものです。まず冒頭で強く訴えたいのは、福祉避難所の通信・電源対策は「善意」でも「寄付」でもなく、人命と情報を守るための必須インフラ投資だということ。福祉避難所の通信・電源対策を軽視したままでは、災害時に支援すら呼び込めません。
- 東京都内には3千か所以上の介護施設がある一方、非常用電源設備の導入は1割未満というのが現場感です(長時間運転を前提とした実用レベルの話)。
- 多くの施設では、何かが起これば悲惨な現実が待つ──この前提が十分に共有されていません。
- それを承知の上で介護事業を営んでいるという事実を、利用者も施設もまだ深く理解できていない。
- これは「国や行政の責任」以前に、医療・介護施設側の経営判断と投資の問題です。
痛みを伴う言い方ですが、福祉避難所の通信・電源対策を自院・自施設に実装する覚悟こそが、地域のいのちを守る出発点です。
背景①:通信・電源が同時に落ちると、福祉避難所は「動かない」
災害では、携帯基地局・交換局の停電と非常用発電機の燃料枯渇が連鎖し、広域で通信が長時間不通になります。施設側でも停電が長引けば、電子カルテやナースコール、酸素濃縮器・吸引器、エレベータ、非常通報装置、Wi-Fi/ルータといった要の機器が停止。連絡・搬送調整・指示系統が壊れ、結果的に「福祉避難所を開けない/開けても運営継続が困難」となります。
「落ちない電源」と「落ちない通信」が最初の5分を決める
- 無瞬停(無瞬断)の電源で、命に直結する機器と通信を護る。
- 冗長可能な通信(衛星通信等)で、状況共有と支援の呼び込みを確保。
- 継続運転の仕組み(太陽光・外部給電・V2H等)で、長期戦を見据える。
行政の支援が届くまでの“空白時間”をまたぐのは、ほかでもない施設自身の初動です。ゆえに、福祉避難所の通信・電源対策を中核に据えることが、最短経路の解決策になります。
背景②:人員の被災・断水・衛生課題で「開設そのもの」が遅れた
福祉避難所は平時に指定・協定されていても、実際に開くには「開ける人」と「維持できる環境」が必要です。能登半島地震では職員自身の被災・断水・トイレ衛生・感染対策・物資不足などが重なり、開設判断が遅れる/開けない施設が各地で発生しました。つまり「場所はあるが、動かす力がない」。この構造的弱点は、都市部でも条件が重なれば再現します。
想定外を前提にする──訓練・マニュアル・契約の見直し
- 代替要員の確保(多能工化、近隣施設との相互支援協定)。
- 水・トイレ・衛生の即応手順(災害用トイレ、簡易手洗い、消毒ルート)。
- 物資・医療機器の優先順位と持ち出し動線(搬送・エレベータの冗長化)。
背景③:行政は「見えなかった」──情報空白が初動を鈍らせる
発災直後は、電源・通信の途絶が広がると、自治体も全体像を把握できない状態に陥ります。どこで何が起きているのか、誰に何が必要なのか──地図上の点が空白になります。だからこそ、施設側に自前の発信能力(通話・データ・最低限の画像)が必要です。見つけてもらうのを待つのではなく、「こちらは動いている、ここにこれが必要だ」と発信できるかが、支援到達の分水嶺になります。
都市部の現実:東京と愛知でも「同じことが起こり得る」
東京都は施設数が多く、福祉避難所の運営は広域かつ複雑です。非常用照明や消防設備を動かす電源はあっても、長時間にわたって医療・介護・通信まで維持する電源は、まだ十分とは言えません。愛知でも、沿岸部・都市部・山間部で脆弱性は異なりますが、大規模停電+通信断が重なる可能性は常にあります。
結論:地域や建物の条件は違っても、解き方は同じ。まず福祉避難所の通信・電源対策を核に据え、通信の冗長化をセットで整えることです。
解決策:三層で固める「落ちない」設計(無瞬停 → 持続化 → 運用)
私たちが現場で導入を進めているのは、①無瞬停(可搬型大容量UPS)で最重要負荷を守り、②太陽光や外部給電で持続化し、③運用・訓練・点検を回す三層設計です。とくに可搬型で常時インバータ方式の大容量UPSを中核に据えると、停電の0秒目から通信・医療機器・照明を守れます。避難動線に合わせて電源を持っていける柔軟性は、福祉避難所の実運用に強い味方です。
優先するクリティカル負荷(例)
- 通信:衛星通信(例:Starlink)、非常用ルータ/スイッチ、PoE電源、緊急通話。
- 医療・介護:酸素濃縮器、吸引器、経管栄養ポンプ、CPAP、AED、保冷・温熱管理。
- 安全・生活:照明、エレベータ(避難・搬送)、トイレ・給水、最低限の空調。
三層設計の全体像は、内部記事「停電でも“ケアを止めない”電源・通信の考え方」に集約しています。福祉避難所の通信・電源対策の骨子・選定基準・配線の考え方を詳しく解説しています。(内部リンク)
導入ステップ:最短で「使える状態」にするには
1)要件定義(クリティカル負荷の棚卸し)
命に直結する機器、通信・連絡のためのネットワーク機器、避難・搬送のための昇降設備──まずは「止めない機器」を列挙し、同時使用の最大電力(W)と必要時間(h)を明確化します。ここで福祉避難所の通信・電源対策の規模がほぼ決まります。
2)電源アーキテクチャの選定
可搬型大容量UPSを中核に、常時インバータ方式を選定。避難所の動線に合わせて仮設盤や直結アダプタも準備します。太陽光があれば昼間の発電を活用し、V2Hや車載ACなど外部給電で夜間の継続性を確保します。
3)通信の冗長化
光回線が死んでも、衛星通信+非常用ルータで「施設から発信できる」状態を守ります。最低限の画像送信と位置情報、テキストで十分。「ここに何人、何が必要か」が一度送れれば、支援が動きます。
4)運用・訓練・点検
機器は使って初めて戦力になります。月次の短時間訓練、四半期の模擬停電、年次の総合点検を推奨。消耗品(ケーブル・ヒューズ・衛生資材)と台車・搬送用品まで、触れる・動かすの積み重ねが現場力を底上げします。
補助金の活用(東京都/蒲郡市)──“保険”から“設備投資”へ
東京都:社会福祉施設等への非常用電源等 整備促進
非常用電源設備、可搬型蓄電池、V2H、外部給電器などが対象。補助率3/4、上限500万円(年度により変動)。最新情報は東京都の公式情報をご確認ください。公式案内:東京都
蒲郡市:災害時医療等継続支援事業費補助金・災害時福祉避難所運営継続支援事業費補助金
太陽光・蓄電池・可搬型蓄電池(UPS付帯)などが対象。補助率1/2、上限100万円(単体導入)/200万円(太陽光+蓄電一体)。詳細は公式ページをご確認ください。公式案内:蒲郡市(健康推進課)・蒲郡市(福祉課)
これらをレバレッジに、福祉避難所の通信・電源対策を最短で実装し、平時は訓練・イベント電源としても活用すれば、投資回収の道筋が描けます。
まとめ:福祉避難所の通信・電源対策は「いのちと情報」を守る設備投資
- 発災直後の空白時間をまたぐのは、施設自身の初動。
- 無瞬停→持続化→運用の三層設計で、落ちない電源・通信を平時から装備する。
- 補助金を活用し、段階的に導入。今日決めて、最短で動くことが何よりの備え。
関連・内部リンク
▶ 設計の全体像と機器選定の考え方(無瞬停→持続化→運用):停電でも“ケアを止めない”ための設計
参考・外部リンク(制度案内)
- 東京都「社会福祉施設等への非常用電源等の整備補助」:https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/06/2025062012
- 蒲郡市「災害時医療等継続支援事業費補助金」:https://www.city.gamagori.lg.jp/site/hokencenter/saigaiiryou.html
- 蒲郡市「災害時福祉避難所運営継続支援事業費補助金」:https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/fukushi/fukushihinanjohojo.html
参考・出典リスト(外部リンク)
- 福祉避難所の開設遅れ・運営困難: 朝日新聞(2024/1/13) | 朝日新聞(2024/1/13)
- 通信断絶の長期化(基地局停電・燃料枯渇): NTT西日本(2024/5/12時点の状況) | 非常災害対策本部資料(2024/1/4) | 総務省WG資料(2024/8/9)
- 広域停電と復旧の長期化(奥能登で顕著): 北陸電力送配電(停電復旧の対応) | 日本自然災害学会誌(2024/) | 経産省+北陸電力 資料(2024/3/29)
- 行政の「情報空白」課題(状況把握の困難): 内閣府 資料(「情報の空白時間・空白地域の解消」)
- 福祉避難所の長期化・帰還できない人の存在: 毎日新聞(2025/6/27) | 福祉新聞(2025/1/17) | 朝日新聞(2025/2/2)
