間違った知識は二次災害に繋がる、電源確保のコツ(ポータブル電源編)
2025.10.06 災害への備え・防災 管理人
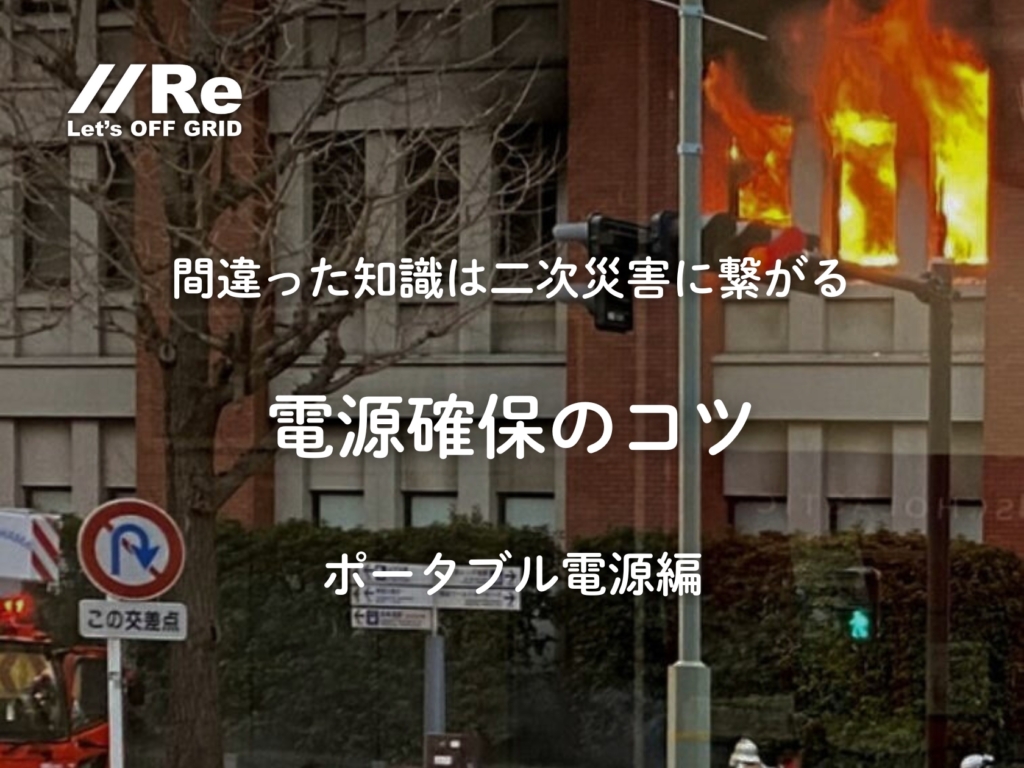
間違った知識は二次災害に繋がる、電源確保のコツ(ポータブル電源編)
停電や断水といった一次災害の後に、誤った使い方が原因で発生する火災・感電・機器破損・データ消失などの“二次災害”。近年は大容量化したポータブル電源(ポータブル蓄電池)の普及に伴い、便利さと同時にリスクも顕在化しています。今回は、読み終えたときに具体的に“何を選び、どう使い、どこで線を引くか”が判断できる状態を目指します。
話題提起:便利さの裏側にある“誤解”が火種になる
「容量は大きいほど安心」「PSEマークがない=違法」「正弦波も疑似正弦波も同じ」「冷蔵庫は定格Wだけ見ればOK」「満充電で保管がベスト」——これらは、現場でよく見かける誤解の例です。容量(Wh)と出力(W)は別物であり、起動電力(サージ)は定格の2〜3倍に達することも珍しくありません。さらに、波形の違い(純正弦波/疑似正弦波)や、充電・保管の温度管理、ケーブル定格など、運用の基本を外すと二次災害が生まれます。誤解を解き、“専門家じゃないからこそ安全第一に”選ぶ方法と使い方を徹底しましょう。
事故事例(外部資料引用)
- 消費者庁:災害時の需要増に伴い、携帯発電機/ポータブル電源の事故が発生。注意喚起資料で基本的な危険要因を周知しています。
携帯発電機やポータブル電源の事故に注意! - 国民生活センター:高エネルギー機器としての取扱注意を継続発信。使い方の初歩的なミスの重なりが事故につながると指摘。
見守り新鮮情報 第519号 - 東京消防庁:リチウムイオン電池火災の実例と注意点を公開。充電方法や外部衝撃、劣化が引き金になるケースを解説。
リチウムイオン電池の火災危険 - 消防庁:リチウムイオン蓄電池に関する通達資料(PDF)。
資料リンク(PDF) - NITE:電池事故の傾向と対策。購入・充電・保管・廃棄の基本を遵守する重要性を強調。
資料リンク(PDF)
なぜ事故が起こるのか?(メカニズムの要点)
1)熱暴走(過充電・内部短絡・外部衝撃)
セル温度が閾値を超えると発熱が自己増幅し、可燃性ガスの発生や電解質分解を伴って発火に至ることがあります。落下・圧潰・穴あけ、高温環境下での急速充電は厳禁。夏季の車内放置は避け、充電は指定温度範囲内で実施します。
2)BMS(電池管理システム)の保護限界
BMSは過充電/過放電/短絡/過熱を監視しますが、規定外の充電器や温度範囲外の運用、長期満充電保管などまで自動で救ってはくれません。ユーザー側の運用責任が残ることを前提にしましょう。
3)インバータと負荷の相性(定格・サージ・波形)
冷蔵庫やコンプレッサ、電動工具などは起動時に大電流が流れ、定格の2〜3倍のサージを要することがあります。純正弦波以外で精密機器を駆動するとノイズや発熱、誤作動の原因になるため、波形と負荷の適合確認は必須です。
日本の規制状況:ポータブル電源本体はPSE対象外
AC(交流)出力を備えたポータブル電源本体は、現行の電気用品安全法(PSE)の直接の規制対象外です(付属のACアダプタ等は別扱い)。経済産業省は「ポータブル電源の安全性要求事項(中間とりまとめ)」を公開し、火災・感電リスクや今後の対応方向を示しています。
参考:経産省:中間とりまとめ/モバイルバッテリーFAQ
結論:PSEの有無だけでは本体安全性を判断できません。第三者試験(UN38.3 / IEC 62133相当 / TÜV等)の明示と、メーカーの安全情報・品質保証を重視しましょう。
どう選ぶ? 安全優先のチェックリスト
A. 容量と時間の見積もり
必要Wh=機器W数×使用時間h。例:100Wを5時間→500Wh。効率や温度損失を見込み、20〜30%の余裕を加算します。
B. 定格とサージの両睨み
冷蔵庫・ポンプ・工具は起動サージが大きい代表格。同時使用の合計Wとサージ耐性を確認し、たこ足配線は避けます。
C. 波形は純正弦波を基本に
精密機器や医療・IT系は純正弦波が前提。疑似正弦波・矩形正弦波は誤作動・発熱の温床になります。
D. 充電・保管・点検
純正充電器・規定電圧/電流・温度範囲の厳守。高温充電・長期満充電保管は避け、50〜60%残量での保管と定期点検を推奨。
E. セル化学と安全性
LFP(リン酸鉄)は熱暴走に比較的強く、サイクル寿命長め。固体電池は電解質固体化により安全性・耐環境性が期待されますが、実装はメーカー差があるため、試験成績と保証条件を確認しましょう。
F. サポート体制
国内窓口・保証年数・リコール対応。非常時に使うからこそ、問い合わせのつながりやすさは見えない安全性です。
製品例:固体電池ポータブル電源「YOSHINO」
固体電解質を用いたアプローチで安全性・エネルギー密度・耐環境性の向上を追求するポータブル電源が「YOSHINO」です。ラインナップやアプリ連携、長期保証など運用性の面でも改良が進んでいます(詳細はメーカー資料をご確認ください)。
参考:YOSHINO公式サイト / TÜV SÜD試験の言及
強み
- 固体電池系ならではの安全マージンと耐環境性の追求
- 純正弦波出力・スマホアプリ・長期保証など運用性
- UN38.3など第三者試験の明示(モデルによる)
留意点(デメリット)
- 一般的なリチウム系より価格帯が高め
- 出力波形・サージ・BMS仕様はモデル差があるため、負荷機器との適合確認が必須
- 「固体電池」は総称であり、具体的な安全設計・試験成績の確認が前提
YOSHINO オンラインSHOP(BASE)
非常時の実運用を想定したモデル選定をサポートしています。
ラインナップはこちら:Re BASE SHOP(YOSHINO取り扱い)
用途(何Wを何時間・同時使用の有無)が分かれば、最短で候補を絞り込み可能です。
ここはポータブル電源“不可”の領域(専用電源へ)
下記は安全・法令・品質保証の観点からポータブル電源の適用外と考える領域です。無理な適用は二次災害や保証外トラブルにつながります。
- 医療機関・社会福祉施設の重要負荷/医療機器:医用規格・接地・EMC・無瞬停・電源品質(CVCF)が必須。
→ 可搬型大容量UPS×CVCF『パーソナルエナジー・ポータブル』 をご確認ください。 - サーバ・証券取引・IT/DX・PLC/FA機器:瞬断や波形歪み・サージに脆弱。
→ 『パーソナルエナジー・ポータブル』(無瞬停・CVCF)とネットワーク冗長の系統設計が必要。 - 建物/施設全体のバックアップ(定置型):系統連系・盤設計・保護協調・保安監督が関係。
→ 太陽光・蓄電池・V2H や 独立電源『パーソナルエナジー』 を検討。
参考資料(外部リンク)
- 消費者庁:携帯発電機やポータブル電源の事故に注意!
- 国民生活センター:見守り新鮮情報 第519号
- 東京消防庁:リチウムイオン電池の火災危険
- 消防庁:リチウムイオン蓄電池に関する通達(PDF)
- NITE:電池事故の傾向と対策(PDF)
- 経産省:ポータブル電源の安全性要求事項(中間とりまとめ)
- 経産省:モバイルバッテリーFAQ(PSE対象範囲)
