間違った知識は二次災害に繋がる、電源確保のコツ(定置型リチウムイオン蓄電池編)
2025.10.08 災害への備え・防災 管理人
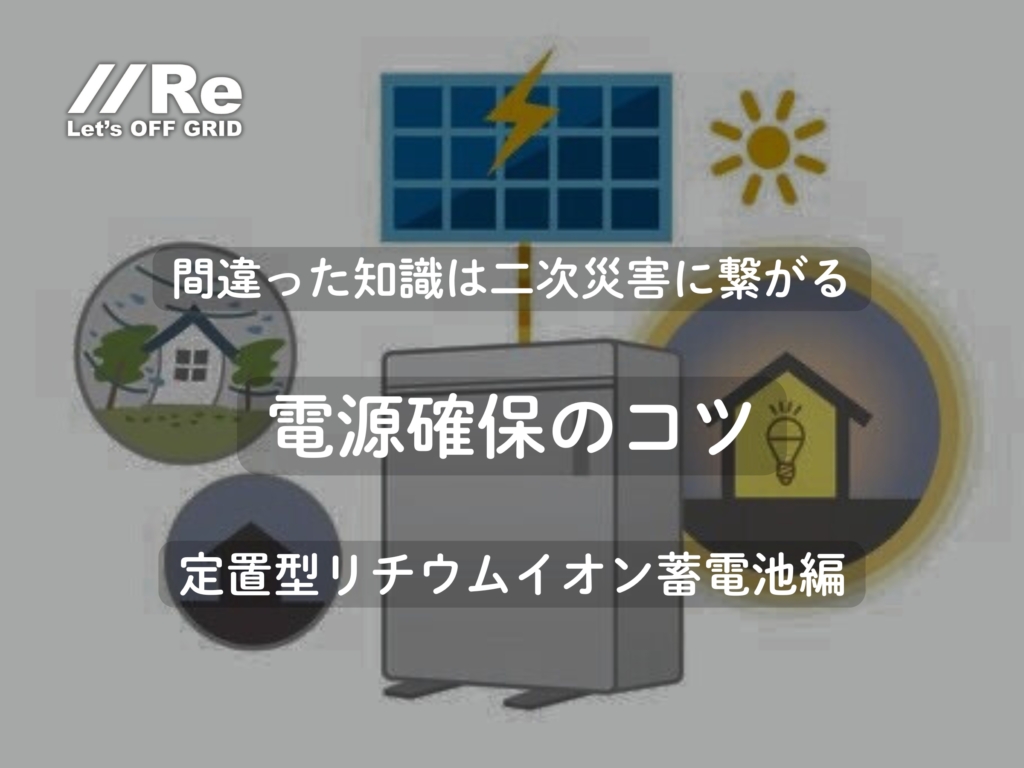
間違った知識は二次災害に繋がる、電源確保のコツ(定置型リチウムイオン蓄電池編)
停電や断水の一次災害後に起こる火災・感電・機器破損などの“二次災害”。この記事は一戸建て向けに定置型リチウムイオン蓄電池(以下、定置型蓄電池)を安全かつ費用対効果よく導入するための設計ポイントをまとめた実務ガイドです。前回(ポータブル電源編)はこちら。太陽光との協調は社内解説ページ太陽光・蓄電池もご参照ください。
まず押さえる“誤解”と基本設計の軸
「容量(kWh)が大きいほど安心」「家まるごと長時間バックアップできる」「太陽光があれば停電中も勝手に充電され続ける」「屋内の好きな場所に置ける」「10年ノーメンテ」——これらは前提が整って初めて成立します。満足度はバックアップ範囲(全負荷/特定負荷)・出力(kW)・容量(kWh)・切替(自立/連系)・設置環境(離隔/防水/換気)がご希望に叶うことで決まります。
事故のメカニズムを“構造”で理解する
1)熱暴走(過充電・内部短絡・外部衝撃)
高温・衝撃・非純正配線などでセル温度が閾値を超えると反応が自己加速。直射日光+通気不良は典型的リスクです。
2)BMS/PCSの保護は万能ではない
過充電・過放電・短絡・過熱を監視しますが、規定外配線や温度範囲外運用、長期満充電保管までは救済しません。機器保護+運用ルール+定期点検が三本柱。
3)“自立/連系”と同時使用
停電時は自立運転へ。全負荷は合計kWがボトルネック、冷蔵庫・電子レンジ・エコキュート再起動のサージで遮断することも。特定負荷で重要回路を確実に守る設計が現実的です。太陽光との連携は太陽光・蓄電池で基本を整理してください。
蓄電池に関する日本の規格で見るポイント
- 安全は機器単体でなく“システム全体”で評価。
- 設置は消防・建築の考え方と擦り合わせが必要に。離隔・区画・換気・雨掛かり/冠水リスクを評価、必要に応じ自治体と事前協議。
- 運用は取説準拠+年次点検+ファーム更新+リコール確認+停電時の手順共有。
チェックリストで設計する
A. バックアップ範囲(全負荷/特定負荷)
「冷蔵庫・照明・通信・在宅ワーク用コンセント・井戸/給水ポンプ」など落とせない重要回路を先に確定し分電盤で特定負荷化。全負荷は快適だが必要kW/kWhとコストが跳ね上がる。
B. 容量(kWh)の概算と余裕
必要kWh ≒(重要負荷W合計 × 使いたい時間h)÷ 1000。機器効率・温度・経年劣化を見込み+20〜30%の余裕を。例:500W×10h=5kWh → 6〜7kWh目安。昼の太陽光と重ねると体感安心度が上がる(太陽光・蓄電池)。
C. 出力(kW)とサージ
ドライヤー・電子レンジ・エアコン、エコキュート再起動は定格の2〜3倍の突入が起き得る。定格+サージ許容を基準に同時使用シーンから逆算。
D. 自立運転の手順と“誰でも使える”運用
停電時の切替、非常用コンセントの使い方、復電時の戻しは家庭内で共有。紙1枚(またはスマホ共有)にまとめ常備。
E. 設置環境:熱・水・可燃物・配線保護
屋外は直射日光・豪雨・潮風・冠水、屋内は可燃物・換気・離隔に注意。配線/盤内は保護協調(遮断器・SPD)とアースを適切に。
F. 保証・サポート・アップデート
保証年数、窓口の繋がりやすさ、ファーム更新、リコール周知、地域保守網など“見えない安全性”を評価軸に。
費用対効果の見方
- 総額=機器+工事+分電盤(特定負荷化)+申請・試運転・点検。容量・出力・設置条件でレンジが広い。
- 電気代平準化:高単価時間帯は放電、安価時間帯に充電。太陽光併用で効果が安定。
- レジリエンス:年数回の停電でも「通信・冷蔵庫・照明は落とさない」だけで生活満足度が大きく向上。
“定置型が向いている/向いていない”の線引き
向いている:冷蔵庫・照明・通信・在宅ワーク用コンセント・井戸/給水ポンプなど暮らしの基礎。太陽光併用で夜間安心度UP(太陽光・蓄電池)。
向いていない:医療機器・サーバ/NAS・証券端末・PLC等。無瞬停×CVCFが大前提 → 『パーソナルエナジー・ポータブル』
蓄電池導入に向けた最短ルート
- ヒアリング:生活時間帯・停電時優先度・在宅ワーク・井戸/EV・太陽光の有無。
- 要件定義:回路(特定/全負荷)、必要kW/kWh、設置場所(離隔/換気/屋外屋内)、将来拡張。
- 設計・見積:ハイブリッドPCS、自立切替、分電盤改修、CT計測、HEMS、太陽光連携、過電流保護・SPD。
- 施工・試運転:実負荷の自立運転テスト、復電時手順、家族向け操作説明。
- 運用・点検:年次点検、ファーム更新、家庭内“停電訓練”。
参考・外部リンク
全負荷と特定負荷、どちらが良い?
重要回路を確実に守るなら特定負荷が基本。全負荷は快適だが必要kW/kWhとコストが増え、同時使用の制約も大きくなります。
停電中、太陽光で自動充電できる?
機器仕様と設定に依存。自立運転の切替手順、非常用コンセントの使い方、復電時の戻しを事前に家族で共有しておくのが安全です。
容量はどのくらい必要?
目安は「必要kWh≒(重要負荷W合計×使いたい時間h)÷1000」。効率・温度・経年劣化を見込んで20〜30%の余裕を持たせると運用が安定します。
