非常用自家発電設備だけでは守れない──72時間“無停止”という思い込み
2025.09.12 停電対策・BCP 医療機関 社会福祉施設 管理人
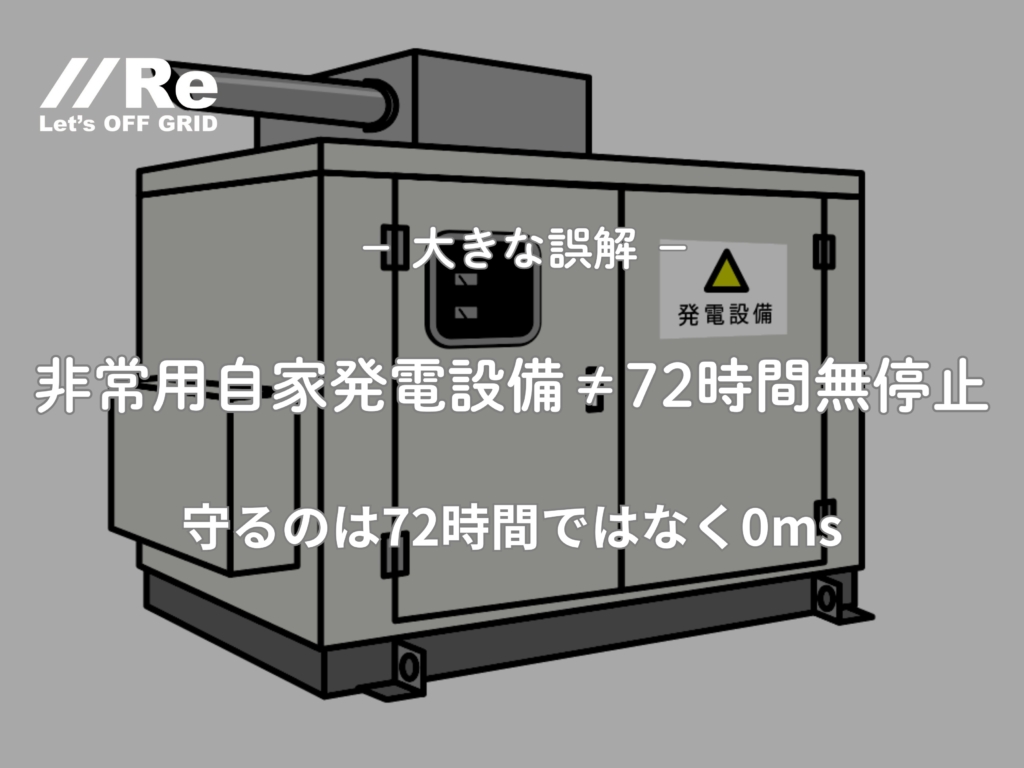
非常用自家発電設備だけでは守れない──
72時間“無停止”という思い込みとCVCF必須の理由
非常用自家発電設備(いわゆる非常用発電機、以下「非常用自家発電設備」)があれば72時間“無停止”で連続運転できる──そんな言い回しが現場に定着しているように見受けられます。しかし、これは危険な前提です。法令やガイドラインが原型として想定しているのは、避難・初期対応に必要な短時間の非常電源であり、長時間連続運転の製品保証や電源品質(定電圧・定周波・正弦波)までを一体で満たすという話ではありません。
さらに、医療現場・証券取引・IT/DX・製造業など高感度な機器を扱う現場では、コンマ何ミリ秒(0.数ms未満)という瞬停(瞬断・瞬時電圧低下)が命取りになります。非常用自家発電設備が設置されていても、起動・負荷投入・再同期の局面では波形の乱れや一時的な電圧・周波数の変動が避けられません。ゆえに非常用自家発電設備は冗長性を担う“母艦”であり、負荷の“入口”にはCVCF(定電圧定周波)を満たす常時インバータ方式UPSを中核に据える──これが「止めない設計」の現実解です。
目的:72時間“無停止”神話の是正と、非常用自家発電設備×CVCF/UPSを前提とした“停電ゼロ設計”のロードマップ提示。
「72時間無停止で連続運転できる機種がある」は本当か?
市場には“長時間連続運転を志向した仕様”が存在することは事実ですが、一般的な建築設備分野で製品保証として「72時間無停止」をうたう非常用自家発電設備は標準ではありません。長時間運用には、燃料の調達・貯蔵規制(危険物)、潤滑油・冷却系の管理、排熱・排気・騒音対策、点検・監視体制など多数の制約を同時に満たす必要があります。つまり「非常用自家発電設備=72時間」という短絡的な解釈は、設計・運用・法規制の実態から外れているのです。
そもそも多くの施設で重要なのは、最初の数十秒〜数分の“無瞬断・高品質”の橋渡しです。ここを落とせば、電子カルテ、取引端末、サーバやネットワーク、監視録画、製造ラインの制御器などが誤動作・再起動・データ毀損に直結します。したがって入口にCVCF(常時インバータUPS)を置き、非常用自家発電設備と協調させるのが王道です。
“止めない”ための三層防御:CVCF/UPS × 非常用自家発電設備 × 蓄電・太陽光
層1:CVCF/常時インバータUPS(0ms切替/電源品質の担保)
- 平常時からAC→DC→ACの二重変換で電圧・周波数・波形を整流し続ける。
- 瞬停・サグ・サージを0ms切替で吸収。負荷の起動突入や短時間ピークも緩和。
- 対象:電子カルテ/PACS/仮想基盤/コアSW・FW・VPN/売買端末/制御器/冷蔵・薬剤・検体 等。
層2:非常用自家発電設備(“母艦”としての継続供給)
- ATS/AMFで自動投入。ただし起動・再同期時のゆらぎはUPS層で吸収する前提。
- 72時間“無停止”を前提にしない。燃料・潤滑・排熱・監視・規制を踏まえた現実設計へ。
層3:蓄電池+太陽光(補給途絶・長期化の延命策)
- 燃料配送が止まった際の最後の防波堤。赤系負荷(止めない負荷)に電力を集中投下。
- 昼は太陽光で補充、夜は蓄電で凌ぐ。縮退運転の行動計画とセットで効果を最大化。
「止めない設計」の基本解説は関連記事を参照:医療・福祉の“止めない設計”の考え方。
現場別のポイント(医療/福祉/証券/IT・製造)
医療機関(無床クリニック〜中小病院)
- 負荷の色分け:赤(絶対止めない)/黄(できれば止めない)/青(止まっても可)。
- 赤は常時インバータUPSに集約。既設非常用自家発電設備とは静止形切替で協調。
- 冷蔵・陰圧・酸素など設備系は個別UPS+系統切替で二重化。
社会福祉施設(特養・福祉避難所)
- 夜間のナースコール、非常通報、最低限の照明・通信を赤/黄に寄せる。
- 長期化に備え蓄電+太陽光を付加。縮退運転の行動計画を文書化し訓練。
- 補助制度の活用で初期費用を圧縮(下記リンク参照)。
証券・ディーリングフロア
- 売買端末・音声記録・低遅延回線・VPN集中を赤に。UPS二重化+回線デュアルが定石。
- VLAN分離で業務/庁内/来訪者系を隔離。電源と通信の二輪駆動の冗長を。
IT・製造(データ室・ライン制御)
- 認証/DNS/DHCP/vCenter等の基幹を赤に。制御器はUPS+発電機の協調で。
- 監視・ログは縮退中も残せる構成に。復旧手順は紙でも保管。
実装事例や考え方の掘り下げ:CVCF一体型ソリューションの詳解/ 福祉避難所の通信・電源対策と補助金
設計のステップ(チェックリスト付)
1. 止めない対象の“見える化”
- 業務機能→機器→回路の順で棚卸しし、「何を・どれだけの時間・どの品質で」守るかを定義(SLA)。
- 赤(無瞬断・高品質)/黄(短時間停止可)/青(停止可)に色分け。
2. 入口の無瞬断化(常時インバータUPS=CVCF)
- 赤負荷をUPSに収容し、瞬停/サグ/ハーモニックを遮断。
- 容量は起動突入+切替所要時間+運用余裕で積算。
3. 既設非常用自家発電設備との協調
- ATS/AMFの応答、負荷バランス、排熱・排気、燃料・潤滑の管理を実査。
- 試験は業務影響の少ない時間帯に計画。手順書は印刷保管し訓練。
4. 長期化への備え(蓄電+太陽光+縮退運転)
- 燃料補給が滞った前提で、赤だけを長時間維持する手順を設計。
- 昼夜の電力バランスを想定して縮退時の運用KPIを設定。
5. 保守・訓練・点検
- 月次・年次の点検/実負荷試験、担当替えに備えた教育・訓練を定例化。
- ログ管理・交換部材の在庫ルールを明文化。
まずは関連記事で全体像を掴む:“止めない設計”総論/ CVCF/UPSの要点と事例/ 福祉避難所×補助金の実務
補助制度の活用(東京都/蒲郡市)
東京都:社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業
東京都は、社会福祉施設の非常用電源・関連機器の整備を後押しする制度を公開しています。対象機器やスケジュール等は公式サイトをご確認ください:事業公式サイト(東京都)。
愛知県蒲郡市:災害時福祉避難所 運営継続支援 事業費補助金
蒲郡市は福祉避難所の電源確保(蓄電・太陽光・可搬型蓄電池等)を支援しています。最新情報・要件は市の案内をご確認ください:蒲郡市公式ページ。
制度は年度で見直されます。要件・期限・上限額は必ず原典でご確認ください。
よくある質問(要点のみ)
Q1. 「72時間無停止で連続運転できる非常用自家発電設備」があると聞いた
特殊用途の長時間仕様は存在しますが、一般の建築設備に一律で当てはめるのは危険です。燃料・潤滑・排熱・騒音・点検・監視、そして法規制を満たす総合設計が必要です。まずは入口の無瞬断化(CVCF/UPS)から。
Q2. 非常用自家発電設備があるからUPSは不要?
いいえ。起動・切替・負荷変動に伴う瞬停と波形乱れは避けられません。医療・証券・IT/DX・製造の重要負荷は常時インバータUPS=CVCFで守るのが前提です。
Q3. まず何から始めれば?
「止めない対象の棚卸し→UPS容量の仮決め→既設発電機と協調設計→縮退運転計画」の順で進めるのが最短です。詳しくは関連記事:総論解説/CVCF/UPSの実装/補助金の活用 をご参照ください。
まずは“止めない回路”の設計相談を
「何を・どれだけの時間・どの品質で守るか」が定まれば、必要なUPS容量・発電機容量・燃料/蓄電計画、そして活用できる補助制度が明瞭になります。株式会社Reは、医療・福祉・証券・IT/製造の現場で“止めない”を最短距離で実装するパートナーです。既設の分電盤・発電機・太陽光・蓄電の再活用、段階導入、小規模PoCからの立ち上げまで、お気軽にご相談ください。
オンライン・現地どちらも対応。守秘義務契約(NDA)も可能です。
